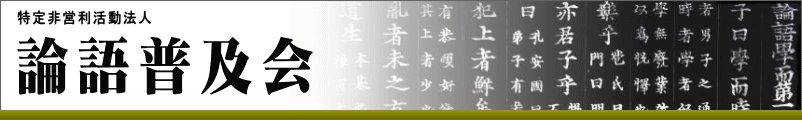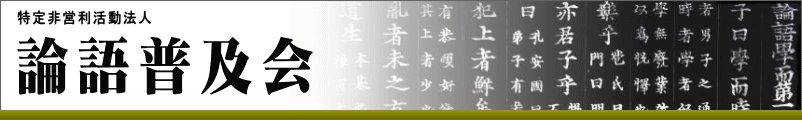| 今月の論語 (2025年10月) |
|
巍巍乎天(ぎぎこてん)
子(し)曰(のたま)わく、
大いなるかな堯(ぎょう)の君(きみ)たるや。
巍巍乎(ぎぎこ)として、
唯(ただ)天(てん)を大いなりと爲(な)す。
唯堯(ぎょう)之(これ)に則(のっと)る。
子曰、大哉、堯之爲君也。巍巍乎、唯天爲大。唯堯則之。
(泰伯第八、仮名論語一〇七頁)
|
|
〔注釈〕先師が言われた。「なんと堯の君徳は大きいことであろう。真に荘厳で偉大なものは天のみである。そして唯堯のみがひとりその偉大さを共にしているのだ」
〔和歌〕大なるは 天か大なる 堯の德 はかり知れざる 君がそのわざ (見尾勝馬)
会長 目黒泰禪
高い山を表す「山部」の漢字は色々ある。諸橋轍次著『大漢和辞典』には「山部」の漢字が300字もあり、そのうち「たかし」と訓読みされる代表的な字だけでも、「屹(きつ)・岌(きゅう)・岱(たい)・岳(がく)・峨(が)・峻(しゅん)・崇(すう)・崒(しゅつ)・崚(りょう)・嵩(すう)・嶽(がく)・巍(ぎ)」などがあげられる。また中国最古の辞書といわれる『爾(じ)雅(が)』には「喬(きょう)・嵩・崇は、高なり」とあることから、「嵩」と「崇」は山だけでなく、人物や自然万物の高さ、ひいでたさま、とうとさの意味に使われていたのがよく分かる。
『論語』の泰伯篇に、孔子が「巍」を重ねて「巍巍乎(ぎぎこ)」(例えようもなく偉大である)として、古代の聖天子の堯(ぎょう)舜(しゅん)禹(う)の政治を表現した章句が二章続く。「なんと堯の君德は大きいことであろう。巍巍乎としているのは天のみである。そしてただ堯のみがひとりその偉大さを共にしている」「巍巍乎だなあ、舜や禹が天下を治められたのは」と言われた。
ところで、大学受験のために斜め読みした夏目漱石著『三四郎』に、熊本からの小川三四郎と一別以来久しぶりに会った東京の広田先生との会話がある。
「君、不二山(ふじさん)を翻訳して見た事がありますか」と意外な質問を放たれた。
「翻訳とは……」
「自然を翻訳すると、みんな人間に化けてしまうから面白い。崇高だとか、偉大だとか、雄壮だとか」
三四郎は翻訳の意味を了した。
「みんな人格上の言葉になる。人格上の言葉に翻訳出来ない輩(もの)には、自然が毫(ごう)も人格上の感化を与えていない」
喜寿になって再読すると、十代当時は富士山を翻訳出来ない輩の一人であったことがよく判る。社会人になってから二度富士山に登ったが、『三四郎』の広田先生の質問はすっかり忘れていた。しかし、ずしりと胸にひびいた翻訳ならあげられる。藤田東湖の『正気(せいき)の歌(うた)』にある「天地正大(てんちせいだい)の気(き)、粹然(すいぜん)として神州しん(しゅう)に鐘(あつ)まる。秀(ひい)でては不二(ふじ)の嶽(たけ)と爲(な)り、巍巍(ぎぎ)として千秋(せんしゅう)に聳(そび)ゆ」である。
|
|