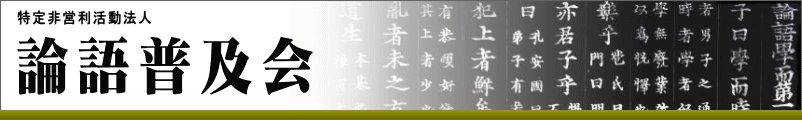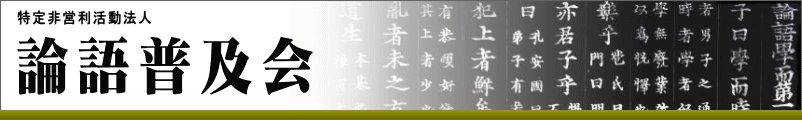| 今月の論語 (2025年5月) |
|
読書為学(どくしょいがく)
子路(しろ)曰わく、民人(みんじん)有り、
社稷(しゃしょく)有り、何ぞ必ずしも
書を讀(よ)みて然(しか)る後に學(がく)と爲(な)さん。
子路曰、有民人焉、有社稷焉。何必讀書、然後爲學。
(先進第十一、仮名論語一五四・一五五頁)
|
|
〔注釈〕子路は「治めるべき人民もいますし、祭るべき土地の神や穀物の神もあります。どうして机の上で書を読むだけが学問でありましょうか」と言った。
〔和歌〕社稷(しゃしょく)あり 民草生(お)へば 學ばずも 宰(さい)たらしめよ 心おきなく (見尾勝馬)
今月の論語 会長 目黒泰禪
今年で戦後八十年になる。昭和二十年三月十日の東京大空襲の直後、東京大学医学部でのひとこまに、防空壕で皮膚科教授の太田正雄(詩人、木下杢太郎(もくたろう))が八人の学生に語りかけるシーンがある。
「こういう時局だからこそ、勉強しなくちゃいけない。朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり。いま、まさに否応なしにその状況に置かれているんだ」と言って、さらにこう続けた。
「君たちは知識と知恵を区別しなくてはならない。知識は、人間が知的活動を続ければ続けるほど無限に増えてゆく。でもいくら知識を積み重ねても、それでは知識の化け物になるだけだ。それではいかん。人間のためになるようにするには、知恵が必要だ。では知恵を学ぶにはどうすればいいか。古典に親しむことだ。古典には人類の知恵が詰まっている」そう言うと、杢太郎は立ち上がり、風のようにさあっと去って行った。(立花隆著『天皇と東大』より)
この杢太郎と相反することを言った弟子の子路が、孔子にたしなめられた場面が『論語』先進篇にある。
子路が年若い子羔(しこう)を費(ひ)という町の代官に推挙しようとした。孔子は「(もっと学問をすべき子羔を大役に当らせては)かえって本人をだめにするのでは」と意見をされた。子路はこれに反発して「治めるべき人民もいますし、祭るべき土地の神や穀物の神もあります。何も読書だけが学問ではありますまい」と言った。孔子は「これだから私は口達者な人物をにくむのだ」と言われた。
孔子は晩年に『易経』を愛読され、韋編三たび絶え、鐵擿(てつてき)三たび折れ、漆書(しつしょ)三たび滅すほどであった。伊與田覺先生はお母様を亡くされた七歳から百一歳まで『論語』を素読された。七十歳で『仮名論語』を墨書され発刊。これを機縁に、論語を家毎に備え家族が和やかに、素読を楽しむような家庭的雰囲気を作ることを目標として論語普及会を設立された。この一月二十六日に急逝された私の畏友、山友達の赤木孝志氏はいつも『正法眼蔵随聞記』をルックザックに詰め、テントでも山小屋でも必ず開いておられた。批評家新保祐司氏は著書『ブラームス・ヴァリエーション』に、二十四年間勤務した大学には、いつも黒表紙の『文語訳新約聖書(詩篇付)』を「鞄に入れて持ちまわった」と記す。この様に古典に親しみたいものである。
|
|