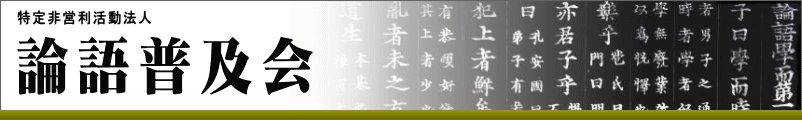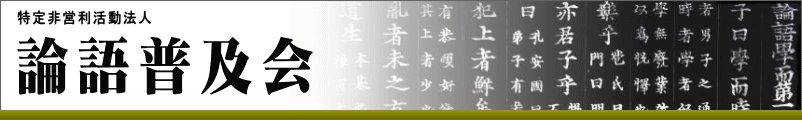| 今月の論語 (2025年3月) |
|
唯恐有聞(いきょうゆうぶん)
子路(しろ)、聞くこと有りて、
未(いま)だ之を行うこと能(あた)わざれば、
唯(ただ)聞く有らんことを恐(おそ)る。
子路有聞、未之能行、唯恐有聞。
(公冶長第五、仮名論語五六頁)
|
|
〔注釈〕子路は、一つの善言を聞いて、まだそれを行うことができないうちは、更に新しい善言を聞くことを恐れた。
〔和歌〕聞くなべに 行ふ子路の なやみこそ たゞきかざらむ ことをおそれし
(見尾勝馬)
今月の論語 会長 目黒泰禪
仁侠の弟子・子路は、孔子から教えを聞けば必ずそれを実行した。それ故、一つの教えを聞いてまだ実践できないうちは、次の新しい教えを聞くことを恐れた(公冶長篇)。単に知識を得るために孔子に随っているのではない。敬愛する師の道を実践せんがため随っていた。実践なければ何の仁ぞ、何の義ぞ、との弟子であった。
その二千年後に、王陽明(明の時代)が「知りて行はざるは只だ是れ未だ知らざるなり」(『伝習録』巻上)と、致良知、知行合一を説く。子路はまさに王陽明の先達である。
それから三百年後、大塩平八郎(江戸後期、号は中斎)は、自ら「吾れ姚江(王陽明)の良知を致すの教を奉ず」(『洗(せん)心(しん)洞(どう)箚(さつ)記(き)』下)と述べ、良知を致すことは、他者の痛みを痛みとしてうけとり、ひたすらその救済につとめることであるとする。「其の義に当りてや、其の身の禍福生死を顧(かえり)みずして果(か)敢(かん)に之を行ひ、其の道に当りてや、其の事の成敗利鈍を問はずして公正に之を履(ふ)む」と、家塾洗心洞の門弟に訓える。飢えに苦しむ民衆を座視するにしのびず、奸吏奸商を討つために蜂起する。大塩平八郎の乱である。
頃は、吉田松陰(江戸末期、号は二十一回猛士)八歳、西郷隆盛(幕末明治、号は南洲)十一歳である。後に吉田松陰は獄中から「吾れ曽(かつ)て王陽明の伝習録を読み、頗(すこぶ)る味あるを覚ゆ。頃(このご)ろ李氏(李卓吾)焚書を得たるに、亦陽明派にして、言々心に当る。さきに日(にっ)孜(し)(品川弥二郎)に借りるに洗心洞箚記を以てす。大塩も亦陽明派なり。取りて観るを可となす。然れども吾れ専ら陽明学のみを修むるにあらず。但だその学の真、往々吾が真と会ふのみ」と、入江九一(杉蔵)宛の手紙に記す。西郷隆盛もまた大塩の『洗心洞箚記』を愛読する。頭山満が明治十二年に鹿児島の西郷家を訪ねた時のエピソードには、「予(かね)て大西郷が愛読していた『洗心洞箚記』を出して見せてくれたが、幾度も幾度も繰返して読んだものと見えて、紙の取れた所があって、そこは大西郷の自筆で書き入れをしてあった。又別に西郷秘蔵の大塩の書があった。大西郷があんな磊(らい)落(らく)な人でありながら、其書幅に限って非常に立派な表装をしてあった所を見ても、西郷がどのくらい大塩を慕っていたかが判る」(藤本尚則著『巨人頭山満翁』天篇より)とある。大塩の影響は計り知れない。
「国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を涜(けが)してゆく」と、市ヶ谷に起つのが三島由紀夫、五十五年前のことである。我々の世代、今こそ「唯(ただ)聞(き)く有(あ)らんことを恐(おそ)る」。
|
|