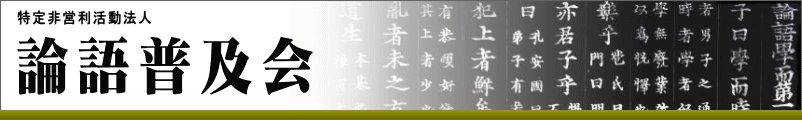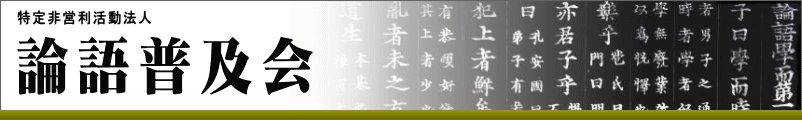| 今月の論語 (2023年2月) |
|
未知生死(みちせいし)
曰(い)わく、敢(あえ)て死を問う。
曰(のたま)わく、未(いま)だ生(せい)を知らず、
焉(いずく)んぞ死を知らん。
曰、敢問死。曰、未知生、焉知死。
(先進第十一、仮名論語一四六・一四七頁)
|
|
〔注釈〕子路がさらに「死とはなんでしょうか」と問うた。先師は言われた。「まだ生もわからないのに、どうして死がわかろう」
会長 目黒泰禪
孔子の弟子子路に限らず、死について問いたいと思うのは、古今東西誰も皆同じである。人はどこから来てどこへ行くのか。聖人賢人のみならず、生あるものは必ず死ぬという理(ことわり)を知っている。諸行無常を知るが故に、死を知りたいと思うのは人間の性(さが)なのではないだろうか。
例年、正月休みはつとめて厚めの本を読むようにしている。それもできるだけ儒学から離れて。オスヴァルト・シュペングラーは言う。「動物は生を知るだけで、死を知らない。しかし動物もまた死の叫びを聞き、死骸を見、腐敗を嗅ぎ出す。かれらは死ぬのを見るが、それを理解しない。…われわれ人間が動物とちがって、世界観として有しているものから出てくるところは、確かに死の認識である」(『西洋の没落』より)。人間だけが認識する死、その死を感じた刹那に不安や恐れを持つ。自らの絶後となる死というものに対する怖れが、宗教や哲学、ひいては科学を発展させた。大戦前の日本で、大川周明や平泉澄そして安岡正篤が、東洋文化から日本精神を論じたように、ドイツではシュペングラーが、世界の歴史と文化からドイツ哲学を論ずる。どの民族にも誇るべき固有の神話があり、民族の歴史があり、文化がある。
孔子は「未(いま)だ生(せい)を知(し)らず、焉(いずく)んぞ死(し)を知(し)らん」(先進篇)と、死の問題よりも先ず生、現実の人生の問題を考えよ、と弟子を諭される。道元も「生(しやう)といふときには、生よりほかにものなく、滅といふとき、滅のほかにものなし。かるがゆゑに、生(しやう)きたらばただこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべし。いとふことなかれ、ねがふことなかれ」(『正法眼蔵』生死より)と言われる。確かに、生きる刹那刹那を大切にしなければと思う。「いま、ここ、ただいま」が大事である。自他ともに「いま、ここ、ただいま」が大事なのである。
国民の生を一顧だにせず、ミサイル発射をする独裁者にも死は来る。国民の死さえものともせず、侵略戦争をする独裁者にもまた滅が来る。一己の死も認識しているだろうし、他者の死ももちろん認識している筈である。そう、人間であるならば。
死につきて 問ひける季路に 答(いら)へまし
生(せい)知らずして 何ぞ死を知ると (見尾勝馬『和歌論語』)
|
|